
医学系と工学系の医療者、研究者や技術者の連携が必要ということは両方の分野で強く意識され、特に21世紀初頭から具体的な連携活動の提案がなされるようになった。その背景としては、日本における医療機器の顕著な輸入超過への懸念があった。
日本の医学や生体医工学分野の諸学会(日本医学会総会、日本生体医工学会、ライフサポート学会、日本コンピュータ外科学会など)で、医工連携の強化に関するシンポジウムの開催や特集号の出版が相次いだ。それらの学会の重鎮の先生方(北島政樹先生、永井良三先生、梶谷文彦先生、伊関洋先生、土肥建純先生、福井康裕先生、藤江正克先生、佐久間一郎先生他)からも、多くのご意見やご提言を頂いた。
工学分野では、2006年に日本機械学会第84期会長の故笠木伸英先生(当時東京大学教授)が日本のものづくりの技術を医療分野に積極的に活用すべく医工連携の必要性を提唱された。
その後、2008年に、日本機械学会第86期会長の白鳥正樹先生(当時横浜国立大学教授)が医工連携推進のための組織設立を具体的に検討すべく提案され、同学会の理事会の企画部会で、次ページに掲載されている医工連携を促進する組織設立の趣意書が作成された。趣意書では、医学系と工学系の学会同士で連携する事が、円滑に医工連携を推進するのによいと提案している。ものづくりの基盤学会である日本機械学会が、医工連携を推進する組織設立のきっかけ役となった。
医療分野とものづくり工学分野との融合を達成するためには、両分野が対等に活用できる場が重要である。そこで、長島昭先生(慶應義塾大学名誉教授、第81期機械学会会長)は、新たに設立する組織では、分野によらず対等に意見交換や情報共有を実行できるように、コモンズというコンセプトを提唱された。「コモンズ」とは、昔から英国等にある共有地の概念で、村の中に一定の区画を共有地として保つ事を互いに申し合わせて、だれでも牧草や樹木を育てて牛を入れたり薪をとってもよいことにする開放地のことである。米国の初期の植民地であるボストンにも、街の中心に長方形の「ボストンコモン」が公園として今も残っている。
以上のような背景の基で、2009年に任意団体として、2013年には、一般社団法人としてコモンズの活動が開始されたが、日本の医工連携を牽引して頂ける最も相応しい方として、北島政樹先生(国際医療福祉大学名誉学長)が、初代理事長として、就任された。北島政樹先生は、慶應義塾大学医学部教授時代に、21世紀COEプロジェクトで医工連携のプロジェクトリーダーをされ、医工連携の教育研究を積極的に推進され、当時の医学部と理工学部を繋ぐ活動にもご尽力されていた。手術ロボット「ダヴィンチ」を日本で初めて導入され、慶應病院にて、ダヴィンチの臨床応用に関する多くの知見を得られていた。北島政樹先生が、日本医工ものづくりコモンズの初代理事長にご就任されて以来、先生のリーダーシップにより、医学系と工学系、並びに産業界の交流が著しく加速するようになった。医と工とが自由な立場で意見交換が出来る雰囲気が醸成されて来た。正に、interdependentや関係が出来るようになってきた。
しかし、これからという矢先に、2019年5 月21日に理事長北島先生が急逝され、コモンズは強力なリーダーを失ってしまった。
2019年の理事会での議論の結果、10年間北島先生から頂いた教えを引き継いで、日本の医工連携をさらに活発にする事は、コモンズの残されたメンバーの責務であるという結論に達し、北島先生のご遺志を繋ぐべく、活動を継続する事とし、現在に至っている。
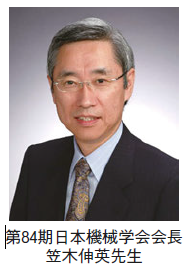 |
 |
 |
 |
 |
日本機械学会理事会で作成された設立趣意書
2009年3 月
日本医工ものつくりコモンズの設立の趣意書
今世紀に入り、高度かつ効率的な医療を実現するために、基礎研究および開発研究に基づく医療工学産業を振興することは、我が国のみならず世界各国の最重要目標の一つとなっている。我が国においても、21世紀を通して持続的発展を遂げるため、我が国の医療工学産業の地歩を固め、さらに、この領域の世界市場において攻勢に転じなければならない。このためには、産官学と医療現場を統合して多分野の英知を結集した研究開発体制を実現し、ここに我が工学技術の粋を集中させる必要がある。
しかしながら、我が国は基礎医学・基礎工学研究の独自性、先進性において諸外国に先駆けているにもかかわらず、その成果が我が国の医療現場に生かされることが少ない。事実、最先端の非侵襲的医療を現にささえている診断および治療用カテーテルや、心臓ペースメーカ、人工関節などの高度医療機器・器具はほぼすべて、欧米諸国からの輸入品に席巻されている。これらの機械・器具・システムは、現在の我が国の技術力をもってすれば容易に産み出すことができる製品ばかりであるにもかかわらず、このような状況となった原因は、従来の医工連携がなかなか実を結ばず、そのため世界に卓越した医療工学産業が我が国において育っていないためである。このような現状は、すでに前世紀から産業界・学界において問題とされてきたが、今世紀に入り事態はますます悪化しつつある。
このような状況を脱するには、これまでの医工連携の種々の試みが必ずしも成果を挙げるに至っていない原因に遡って正す必要がある。その原因の一つは、工学と医学それぞれの方法論・哲学・知的言語体系には極めて異質のものがあり、相互理解が不十分なまま医工連携を進めたことである。
このため、まず、医工連携、医療工学・人間中心技術の開発に携わる人材育成と、医工ものつくり産業に関わる問題点と展望について、工学系の基盤的な各学会の合意により「コモンズ(仮称)」を設置して意見と情報を交換し、その上で技術的に意味のある医工連携共同研究開発を推進する体制の確立へつなげることが必要である。そこで幅広い研究者・技術者が融合して議論し、知的基盤形成などを主として実行出来るコモンズの設置をここに提案する。
このため、医工連携に貢献できる「ものつくり」を基盤とする工学各分野の研究者・技術者が、工学とは異質な学問・技術体系である医学・生物学を客体視するための基礎を固める上で共通の理解と基盤を築くことから始めることが必要である。幸い、工学の分野は極めて広範であるにもかかわらず、そこには共通の理論的・思考的基盤があることから、この作業は比較的容易であると考えられる。
(註) 「 コモンズ」とは、昔から英国等にある共有地の概念で、村の中に一定の区画を共有地として保つ事を申し合わせて、牧草や樹木を育て、だれでも牛を入れたり、薪をとってもよいことにする土地の事である。米国の初期の植民地であるボストンにも、街の中心に長方形の「ボストンコモン」が公園として残っている。